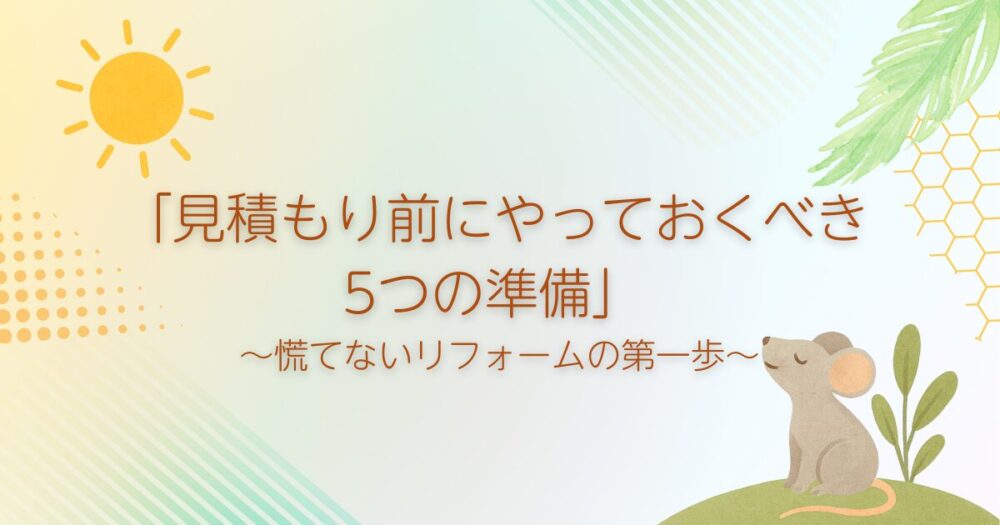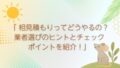🌞 はじめに
「そろそろ水回りをリフォームしたほうがいいかも…」と思い始めたとき、
最初にどこへ相談すればいいのか、何から始めればいいのか悩みますよね。
私の場合、ふらっとショールームに立ち寄ったところ、話が急に進んでしまい、
慌ててしまった経験があります。
そのため、見積もりをお願いする前に自分で少し準備をしておけば、
リフォームがもっとスムーズに進んだのではないかと後悔しています。
この記事ではマンションリフォームで「見積もり前にやっておいたほうがよい」と
感じた5つの準備についてご紹介します。
慌てて工務店に相談する前に、ぜひ一度ご自身の状況を整理してみてください。
✅ 1. 管理規約と工事可能範囲を確認しておく
- マンションには「できる工事/できない工事」のルールがある
→ 玄関ドアの外側や窓サッシなどは共用部分にあたり、変更できないことが多いです。
- 「管理規約」と「使用細則」は必ず確認する
→ 書面が手元にない場合は、管理組合に問合せてみましょう。
- 工事届け出が必要か、書式、提出期限を確認する
→ 多くのマンションで工事開始前に管理組合への届け出が必要です。
- 共用部・駐車場の使い方に関する規定もチェックする
→ 見積もり前の打合せの際に工事期間中に業者が使用可能か確認されます。
- 間取り図(寸法入り)を準備する
→ 業者との打ち合わせやショールームでの相談時に役立ちます。
✅ 2. 困っていること・将来のための希望を“見える化”する
- 現状困っていることを家族で洗い出す
→ キッチン作業台が低い、洗面室のコンセントの位置が低い、ドラム式洗濯機が置けない…など挙げてみましょう。
- 老後の暮らしに備えて「やっておくとよいこと」をイメージする
→ 段差解消、IHコンロへの変更など不安への対応を考えてみましょう。
- 書き出した内容に優先順位をつける
→ 「必須」「できれば」「将来検討」に分類するだけでも大丈夫です。
- 廃棄するものがあればピックアップしておく
→ 解体資材と共に廃棄可能か見積もりの際に相談してみましょう。
- 紙やノートなどにまとめ、目で見える形にしておく
→ 打ち合わせやショールームで相談するときも判断の基準になりブレずに進められます。
✅ 3. 予算の“上限ライン”を決めておく
- 「ここまでは出せる」という金額の上限を決めておく
→ 最初に予算枠が決まっていれば、必要・不要の判断もしやすくなります。
- 老後生活の資金計画をたてておく
→ 退職後、年金生活に入ると収入が限られます。老後の備えを削らない範囲で考えるのが重要です。
- 費用相場をざっくり把握しておく
→ 浴室50万~150万円、キッチン 100万~200万円、洗面所30万~70万円(出典:TOTOサイト)などネットで検索できます。
- 補助金・助成制度が使えるかチェックする
→ 介護保険、自治体の住宅改修助成など、意外と知られていません。
✅ 4. ショールームで実物を見て“イメージを具体化”する
- カタログでは分からない、使用感・素材感を体験できる
→引き出しの開閉、扉面材の質感、浴槽の高さなどは体験すると印象が変わります。
- 間取り図を持って相談してみる
→ 「この浴室ユニットはうちに入るか?」「梁の回避策は?」などの具体的な話ができます。
- 設備の定価ベースでの価格感をつかんでおく
→ 材質やオプションによって価格が大きく変わることを知っておきましょう。オプションを加えた設備の定価価格を算出してもらえます。
- ショールームが近くにない場合はYouTubeやバーチャルツアーを使ってみる
→ LIXIL、TOTOなどが豊富に動画を公開しています。
💡 見て触って「これは要る・要らない」を判断するだけで、予算も計画もぐっと現実的になります。
✅ 5. 工務店の候補をいくつかリストアップしておく
- マンションに対応している業者に絞って情報収集する
→ 戸建てと違い、管理組合との連絡や共用部対応の経験が重要です。
- ネットや口コミで「マンションリフォームの実績があるか」を確認する
→ リフォーム比較サイトを活用したり、自店舗のサイトで実例集をみてみましょう。
- ショールームで提携業者についてたずねてみる
→ 各メーカーの提携施工店からの紹介は、信頼性が高く相談もしやすいです。
- いきなり1社に決めずに、比較するために複数候補を持つ
→ 「この業者がいいかも」と思っても、他と比べて初めて分かることもあります。
🌞 おわりに|焦らず、まず「自分の軸」を持つことから
リフォームは、ただ設備を新しくするだけではなく、
これからの自分たちの暮らしに合った形に整える大きな機会です。
だからこそ、「とりあえず業者に相談」ではなく、
自分の中で方向性や優先順位を整理した上で相談することを、私はおすすめしたいです。
この5つの準備は、今すぐ始められることばかり。
次回以降は、それぞれのステップを私の体験も交えて詳しくご紹介していきます。